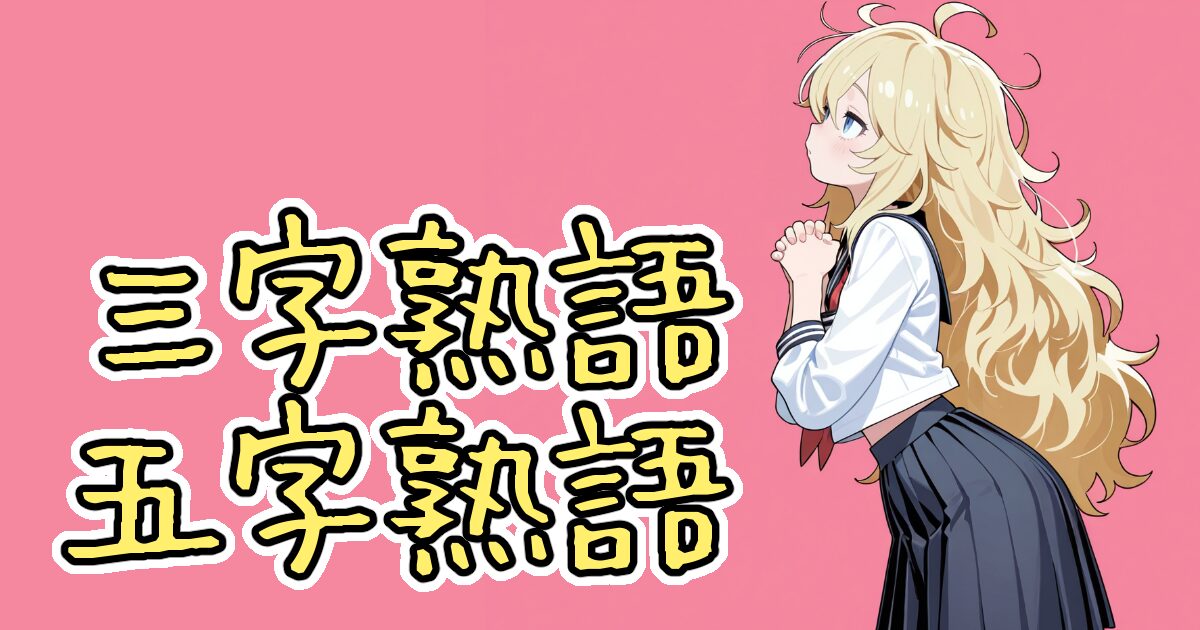日本語には、漢字のみで成り立つ熟語が数多く存在します。
有名なものは四字熟語ですが、三字や五字の熟語も多く存在します。
この記事では、普段使いから教養を深めるまで、さまざまな場面で心を豊かにする厳選された三字熟語と五字熟語をご紹介します。
今回は50音順に紹介していきます!

- 『三字熟語』
- 『五字熟語』
- 井戸端会議(いどばたかいぎ)
- 一姫二太郎(いちひめにたろう)
- 運命共同体(うんめいきょうどうたい)
- 温良恭倹譲(おんりょうきょうけんじょう)
- 御手並拝見(おてなみはいけん)
- 騎士道精神(きしどうせいしん)
- 奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)
- 喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)
- 御都合主義(ごつごうしゅぎ)
- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- 自意識過剰(じいしきかじょう)
- 自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
- 地水火風空(ちすいかふうくう)
- 治国平天下(ちこくへいてんか)
- 二十四節気(にじゅうしせっき)
- 日々是好日(にちにちこれこうじつ)
- 白髪三千丈(はくはつさんぜんじょう)
- 万物光輝生(ばんぶつこうきをしょうず)
- 必要不可欠(ひつようふかけつ)
- 非理法権天(ひりほうけんてん)
- 不完全燃焼(ふかんぜんねんしょう)
- 武士道精神(ぶしどうせいしん)
- 水急不月流(みずきゅうにしてつきをながさず)
- 妙言無古今(みょうげんにこきんなし)
- 明月流素光(めいげつそこうをながす)
- 三十一文字(みそひともじ)
- まとめ:四字熟語だけじゃない漢字の熟語
『三字熟語』
三文字の漢字で成り立つ熟語『三字熟語』を紹介します。
あ、アイちゃんとエリカちゃんがいますね。


どこに?
逃げ足が速いエリカちゃんは韋駄天。
へそ曲がりなアイちゃんは天邪鬼です。

ぐぬぬ。

値千金(あたいせんきん)
意味
非常に価値のあること。
「千金に値する」という意味から、それだけの価値がある、滅多にない貴重な機会や物事を指す際に使われます。
天邪鬼(あまのじゃく)
意味
人の言うことにわざと逆らうひねくれ者。
民間信仰における鬼や妖怪の一種で、転じて、素直でなく、他人の意見に逆らったり、わざと反対の行動をとったりする人を指すようになりました。
韋駄天(いだてん)
意味
非常に足が速い人。
仏教の神である韋駄天が、足が速く仏舎利(釈迦の遺骨)を瞬く間に回収したという伝説に由来します。
一隻眼(いっせきがん)
意味
物事の本質を見抜く優れた眼力や識見。
表面的な情報に惑わされず、奥底にある真実や本質を見抜く洞察力を指します。
金字塔(きんじとう)
意味
偉大な業績や不朽の作品。
古代エジプトのピラミッド(金字塔)のように、永く後世に残る素晴らしい功績や建造物を比喩的に表現する際に使われます。
月天心(げってんしん)
意味
月が天の中央にあること。夜が更け、月が空高く輝く情景。
「天心」は空の真ん中を意味し、澄み切った夜空に月が一点の曇りもなく輝く、静謐で美しい情景を表します。
外連味(けれんみ)
意味
はったりやごまかしのうまさ。見せかけの技巧。
歌舞伎などで、観客を惹きつけるための奇抜な演出や仕掛けを指す言葉でした。
それが転じて、人を驚かせるための技巧や見栄を張ることを意味します。
克己心(こっきしん)
意味
自分の欲望や感情に打ち勝ち、自らを律する心。
目標達成のためや、誘惑に打ち勝つために必要な心の強さを指します。「己に克つ」という儒教の教えが背景にあります。
試金石(しきんせき)
意味
物事の真価や人の力量を試すもの。
金と銀の品位を調べる際に使う石(試金石)のように、あるものが本物かどうか、その価値や能力がどれほどのものかを判断するための基準や機会を意味します。
四天王(してんのう)
意味
仏教の四方位を守護する神々。転じて、ある分野で特に優れた四人の人物。
多聞天、増長天、広目天、持国天の四天王が由来です。転じて、ある集団や分野で特に抜きん出た四人を指すようになりました。
守破離(しゅはり)
意味
武道や芸術などにおける修行の段階を示す言葉です。
師の型を守り、それを破って独自性を出し、最終的には型から離れて自由になること。
日本の伝統芸能や武道、芸道などにおいて、稽古や修行の段階を示す言葉として広く使われます。段階を踏むことの重要性を説いています。
修羅場(しゅらば)
意味
激しい争いや混乱が起こっている場所や状況。
仏教の「修羅」は争いを好む鬼神であり、修羅の住む世界「修羅道」は争いが絶えない場所とされます。
そこから、激しい争いや混乱の現場を指すようになりました。
正念場(しょうねんば)
意味
勝負や成否の分かれ目となる大切な局面。
成功するか失敗するかの最も重要な局面、あるいは最も苦しい局面を指す際に使われます。ここを乗り切れば道が開けるというニュアンスを含みます。
序破急(じょはきゅう)
意味
能楽などにおける構成原理で、導入・展開・結末という時間の流れを表す。
世阿弥の能楽論で示された概念で、物事を構成する三段階のリズムやテンポを指します。文章、音楽、日常の動作など、様々な場面に応用されます。
新展開(しんてんかい)
意味
新しい局面が開けること。
物事が新たな方向へ進展することや、予期せぬ新しい状況が始まることを表します。
静寂観(せいじゃくかん)
意味
静かで落ち着いた心で物事を深く見つめること。
外的な騒がしさにとらわれず、内面的な静けさの中で物事を深く洞察する精神状態を指します。
雪月花(せつげつか)
意味
雪、月、花の三つの自然の美しいものを指し、四季折々の風雅な眺めを表します。
日本人が古くから愛でてきた自然の象徴であり、詩歌や絵画の題材にも多く用いられる、風流な趣を表す言葉です。
大団円(だいだんえん)
意味
物語や出来事の最終的な決着が、めでたく落ち着くこと。
演劇や小説などで、全ての登場人物にとって良い結末を迎えることを指しますが、転じて、現実の出来事が良い形で収まる際にも使われます。
知情意(ちじょうい)
意味
人間の精神活動を構成する三つの要素、すなわち知性・感情・意志。
哲学や心理学などで、人間の精神や行動を分析する際に用いられる基本的な枠組みです。
天王山(てんのうざん)
意味
勝負の分かれ目となるような重大な局面。
羽柴秀吉と明智光秀が戦った山崎の戦いにおいて、勝敗を決定づける要衝であった天王山が語源。勝敗を左右する決定的な局面を指します。
登竜門(とうりゅうもん)
意味
成功への第一歩となる難しい関門。
中国の故事で、黄河の急流にある竜門という場所を登りきった魚は竜になるという伝説に由来します。そこから、立身出世のための難関を突破することを指します。
摩天楼(まてんろう)
意味
非常に高い建築物。
空に手が届きそうなほど高いビルディングを指す言葉で、現代的な都市の象徴とも言えます。
名伯楽(めいはくらく)
意味
馬の良し悪しを見分ける名人。転じて、人の才能を見抜き育てるのがうまい人。
中国の春秋時代の馬の鑑定士、伯楽に由来します。その才能から、隠れた才能を見つけ出し、伸ばす能力のある人を指します。
幽玄美(ゆうげんび)
意味
奥深く趣があり、言葉では言い表せないほど微妙で美しい趣。
日本の伝統的な美意識の一つで、直接的な表現を避け、暗示や余韻によって深い味わいや趣を表現する美しさを指します。
老婆心(ろうばしん)
意味
年老いた女性が、あれこれと気遣い、世話を焼くような親切心。転じて、必要以上に心配して忠告すること。
相手のためを思っての忠告や世話焼きですが、時にそれが余計なお世話になることもあるというニュアンスを含みます。
『五字熟語』
五文字の漢字で成り立つ熟語『五字熟語』を紹介します。
五字熟語って結構しらないものが多いんじゃないですか?

そうですね。馴染みのあるものもありますけど、初めて聞くものも多いです。


エリカははじめましてばっかりだよ!
井戸端会議(いどばたかいぎ)
意味
井戸端で女性たちが集まってする世間話。転じて、主婦たちの立ち話。
かつて共同の井戸が生活の中心であった時代に、水汲みの際に交わされた会話が由来。気軽な情報交換や噂話の場を指します。
一姫二太郎(いちひめにたろう)
意味
最初に女の子、次に男の子が生まれるのが理想的だという考え方。
子育てにおいて、最初に女の子で親の手伝いを覚えさせ、次に男の子で家業を継がせるという、昔ながらの理想的な子どもの順序を指します。
運命共同体(うんめいきょうどうたい)
意味
苦楽を共にし、運命を分かち合う集団や関係。
一つの目的や困難に直面し、全員が同じ状況にあるため、互いに協力し合わざるを得ない関係性を指します。
温良恭倹譲(おんりょうきょうけんじょう)
意味
温和で善良、謙虚で慎み深く、人に譲るという五つの徳。
儒教の思想に由来する言葉で、人として目指すべき五つの徳目を示します。
御手並拝見(おてなみはいけん)
意味
相手の腕前や手際を拝見すること。敬意を表す言葉。
相手の技術や能力を見る際に、敬意を込めて使う表現です。これから披露される技を楽しみにしているニュアンスも含まれます。
騎士道精神(きしどうせいしん)
意味
中世ヨーロッパの騎士が持っていたとされる、名誉、忠誠、勇気などを重んじる精神。
現代では、弱者を守る、正義を貫く、約束を守るなど、高潔な倫理観を持つ行動を指して使われることがあります。
奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)
意味
非常に奇妙で、普通では考えられないほど珍しいこと。
「奇妙」をさらに強調した表現で、常識では理解できないような、極めて珍妙な様子を表します。
喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)
意味
喧嘩をした者同士は、どちらも同等の罰を受けるべきだという考え方。
鎌倉時代に定められた法が由来。現代では、どちらか一方を責めるのではなく、当事者双方に責任があるという考え方として使われます。
御都合主義(ごつごうしゅぎ)
意味
自分の都合の良いように物事を解釈したり、行動したりすること。
客観性や公平さを欠き、自分にとって有利なように道理を曲げる態度を批判的に指す際に使われます。
五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
意味
わずかな違いはあっても、本質的には同じであること。
孟子の言葉に由来。戦場で50歩逃げた兵と100歩逃げた兵が、逃げたという点では同じだと論じたことから、程度の差はあれ、根本的には同じような欠点や問題があることを指します。
自意識過剰(じいしきかじょう)
意味
自分のことを気にしすぎること。
他人の目を過度に意識したり、自分の言動がどう思われているかを気に病んだりする状態を指します。
自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
意味
資金繰りが苦しく、自転車をこぎ続けるように、常に動き続けていないと倒れてしまう状態。
企業や個人の財政状態が厳しく、事業を継続するためには常に資金を回し続けなければならない状況を比喩的に表します。
地水火風空(ちすいかふうくう)
意味
仏教における世界の五大要素。
「五大」とも呼ばれ、この世のあらゆるものが、地(固体)・水(液体)・火(熱・エネルギー)・風(気体)・空(空間)の五つの要素から構成されるという思想です。
治国平天下(ちこくへいてんか)
意味
国を治め、天下を平和にすること。
儒教の『大学』に登場する言葉で、自己を修め、家を整え、国を治め、最終的に天下を平和にするという、為政者の理想的な段階を示します。
二十四節気(にじゅうしせっき)
意味
太陽の動きをもとに一年を24等分した、季節を表す区分。
立春、春分、夏至、冬至など、日本の四季の変化や農作業の目安として古くから使われてきた暦の区切りです。
日々是好日(にちにちこれこうじつ)
意味
毎日が好ましい日である、という禅語です。どのような日でも、その日をありのままに受け入れ肯定的に生きる姿勢を示します。
「毎日が素晴らしい日」という意味ではなく、どのような状況であっても、その日一日を大切に、ありのままを受け入れることの重要性を説いています。
白髪三千丈(はくはつさんぜんじょう)
意味
中国の詩人、李白の詩に由来し、愁いのあまり白髪が非常に長くなったという誇張表現。
途方もないほどの長さの白髪を表現することで、極度の悲しみや苦悩、あるいは驚くべき変化を形容する際に使われます。
万物光輝生(ばんぶつこうきをしょうず)
意味
あらゆるものが光り輝きながら生まれるという意。
世界に存在する全てのものが、それぞれの輝きを持ち、生命力に満ち溢れている様子を表します
必要不可欠(ひつようふかけつ)
意味
絶対に必要で、なくてはならないこと。
そのものがなければ成立しない、あるいは大きな支障が生じるほど重要な要素を指す際に使われます。
非理法権天(ひりほうけんてん)
意味
非は理に、理は法に、法は権に、権は天に及ばない。人間の力では及ばない天の道理があるという意。
この世の物事には序列があり、最終的には人の力ではどうにもならない天の道理が最も強いという、古くからの思想を表します。
不完全燃焼(ふかんぜんねんしょう)
意味
物事が完全に終わりきらず、心残りがある状態。
本来の力を出しきれなかった、あるいはやりきることができなかったために、わだかまりが残る精神状態や状況を指します。
武士道精神(ぶしどうせいしん)
意味
武士が持つべきとされる道徳や精神。
義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義などを重んじる、日本の武士階級に特有の倫理規範を指します。
水急不月流(みずきゅうにしてつきをながさず)
意味
水の流れがどんなに速くても、月は流れない。物事の本質は変化しないという意。
外部の状況がいくら変化しても、本質的なものや真理は変わらないという、不動の真理を示す言葉です。
妙言無古今(みょうげんにこきんなし)
意味
優れた言葉には時代を超えた普遍性があるという意。
真に素晴らしい言葉は、いつの時代にも通用し、人の心に響く力を持つことを表します。
明月流素光(めいげつそこうをながす)
意味
明るい月が清らかな光を放つ様子を表します。
澄んだ夜空に輝く月の光が、清らかで美しい情景を描写します。
三十一文字(みそひともじ)
意味
短歌のこと。五七五七七の三十一音からなる日本の定型詩。
和歌の一種である短歌の形式を表す言葉。限られた音数の中に深い感情や情景を詠み込む日本の伝統的な詩形です。
まとめ:四字熟語だけじゃない漢字の熟語
今回は三字熟語と五字熟語を紹介しました。
それぞれが持つ独特のリズムと意味合いで、私たちの言葉の表現を豊かにしてくれますね。
漢字の熟語の持つ奥深い魅力を、ぜひ感じてみてくださいね。